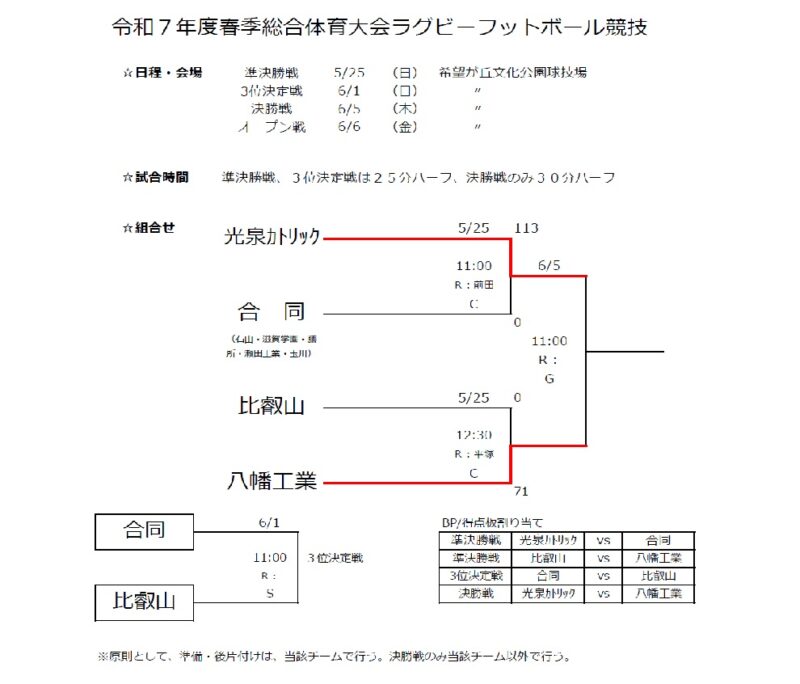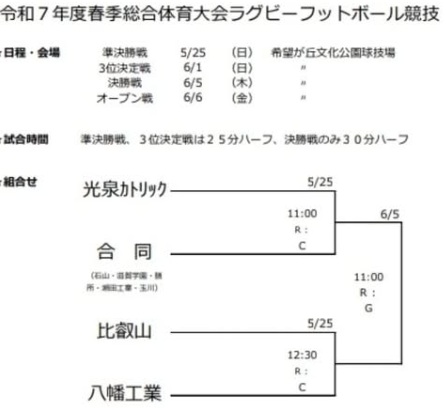2025.05.28 現女子セブンズ日本代表のストレングス&コンディショニングコーチ坂田貴宏氏(1990卒)による現役チーム直接指導の予定
現女子セブンズ日本代表のストレングス&コンディショニングコーチ坂田貴宏氏(1990卒)に膳所高校に来てもらい、グラウンドとトレーニングハウスで現役チームが直接指導を仰ぎます。
日程は次のとおりです。
1日目:6月14日(土)13時開始
2日目:6月15日(日)9時開始
選手のご家族、ラグビーに興味のあるの班員以外の生徒の皆さんも是非見に来てください。
掲載:野口(1985卒)